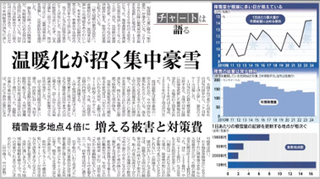山(森)の権利は人が行使する!
 NZのタラナキ山が人間と同等の権利を法的に有するということを当欄(2/16・「森びとオピニオン&アーカイブ」)で知った。背景には、植民地時代の政府が行った土地没収やマオリの権利侵害に対する先住民への権利と文化を尊重する政府の姿勢だと言われている。要するに、タラナキ山の自然保護とか、資源保護とかという考え方ではなく、精神的文化的な存在としての山ということらしい。
NZのタラナキ山が人間と同等の権利を法的に有するということを当欄(2/16・「森びとオピニオン&アーカイブ」)で知った。背景には、植民地時代の政府が行った土地没収やマオリの権利侵害に対する先住民への権利と文化を尊重する政府の姿勢だと言われている。要するに、タラナキ山の自然保護とか、資源保護とかという考え方ではなく、精神的文化的な存在としての山ということらしい。 先日(2/13)、『襤褸の旗』というDVDを観た。描かれていたのは、鉱毒被害に苦しむ農民と田中正造の足尾銅山操業停止を求める闘い(1900年)で、健康被害と命を守る農民の請願闘争だった。しかし、官憲の弾圧(1900年2/13)と、その後の行政の強制執行で村民は村を追い出されてしまい、操業は続いた。ちなみに、今月24日は足尾銅山が閉山(1973年)した。
先日(2/13)、『襤褸の旗』というDVDを観た。描かれていたのは、鉱毒被害に苦しむ農民と田中正造の足尾銅山操業停止を求める闘い(1900年)で、健康被害と命を守る農民の請願闘争だった。しかし、官憲の弾圧(1900年2/13)と、その後の行政の強制執行で村民は村を追い出されてしまい、操業は続いた。ちなみに、今月24日は足尾銅山が閉山(1973年)した。 南半球の先住民マオリの世界観には、「真の文明は山を荒らさず 川を荒らさず 村を破らず 人を殺さるべし」(1912年6/17・田中正造の日記)という精神が貫かれているように感じた。この精神は、未来社会を生きていく次世代の心にも宿ってほしいと願っている。 (アドバイザー・高橋佳夫)
南半球の先住民マオリの世界観には、「真の文明は山を荒らさず 川を荒らさず 村を破らず 人を殺さるべし」(1912年6/17・田中正造の日記)という精神が貫かれているように感じた。この精神は、未来社会を生きていく次世代の心にも宿ってほしいと願っている。 (アドバイザー・高橋佳夫)
 伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ
伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ